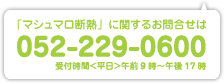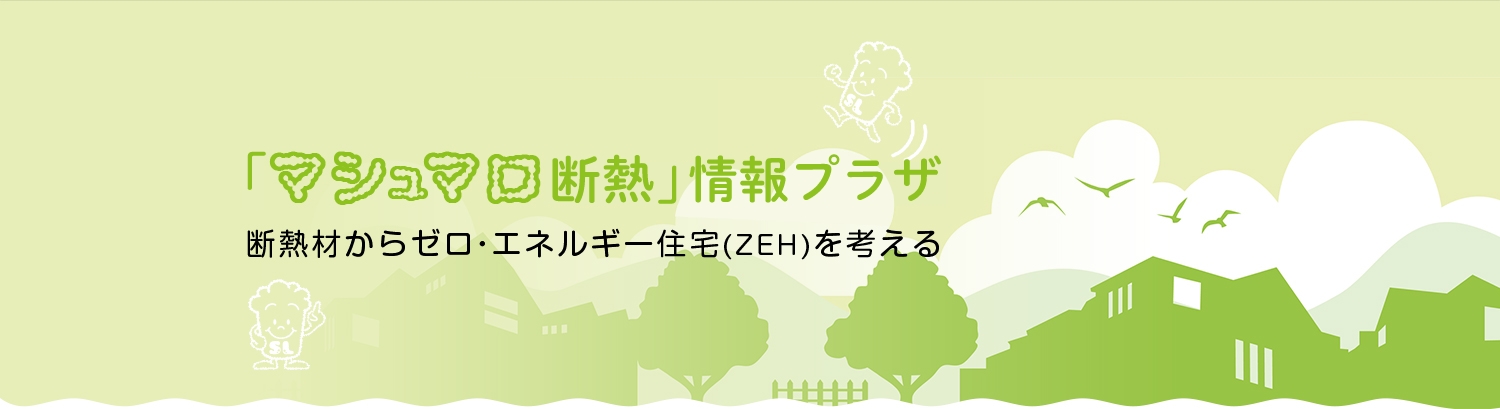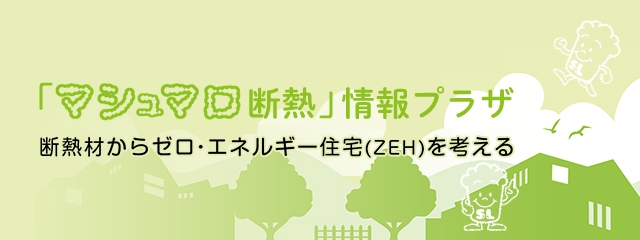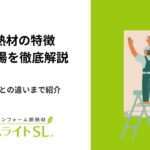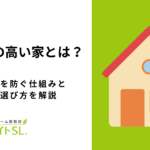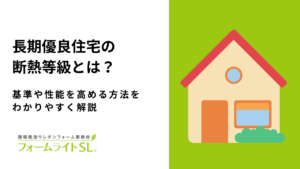
家の快適性と省エネ性を高めたいなら、長期優良住宅の断熱等級を理解することが不可欠です。断熱性能は住宅の寿命や光熱費、居住環境の快適さを左右する重要な指標です。
長期優良住宅として認定を受けるには、断熱等級5以上が求められます。基準を満たすだけでなく、断熱材や窓・気密性まで最適化することで、真冬でも暖かく、真夏でも快適な住まいを実現できます。
この記事では、長期優良住宅における断熱等級の基準と、性能を高めるための具体的な方法をわかりやすく解説します。読めば、断熱等級の考え方から性能向上のポイントまで一貫して理解でき、失敗しない家づくりが可能になります。
|
▼この記事でわかること
|

フォームライトSLは、現場発泡させる吹き付けウレタンフォームです。壁の中を隙間なく断熱材で充填できるため、快適な居住空間を作り出すことができます。断熱等級の最高水準7に対応している点もポイントです。
フォームライトSLの特徴は以下の通りです。
- 優れたコストパフォーマンス
- ランニングコストが経済的
- 断熱工事と気密工事を同時対応できるため工期はおよそ2日間
断熱材選びに迷われている方は、ぜひ詳細が記載されたカタログをダウンロードしてみてください。
目次
- 1 長期優良住宅の断熱等級とは?
- 2 長期優良住宅とは?
- 3 断熱等級とは?
- 4 長期優良住宅には断熱等級5以上が必要
- 5 長期優良住宅の断熱性能を高めるポイント
- 6 断熱材の種類と厚みを最適化する
- 7 換気計画と結露対策で性能を長持ちさせる
- 8 窓やサッシの断熱性能を強化する
- 9 気密性を高めて断熱効果を最大化する
- 10 実測・点検で性能を維持・改善する
- 11 長期優良住宅の断熱性能を高める際の注意点
- 12 断熱等級を上げると建築費用は上昇する
- 13 長期優良住宅の施工実績がある会社を選ぶ
- 14 高性能化は換気計画と必ずセットにする
- 15 長期優良住宅の断熱性能に関するよくある質問
- 16 長期優良住宅に必要な断熱等級はいくつですか?
- 17 断熱等級を上げるとどれくらい費用が変わりますか?
- 18 長期優良住宅はZEH住宅とどう違うのですか?
- 19 断熱性能を高めると夏は暑くなりませんか?
- 20 断熱材の種類で性能はどのくらい変わりますか?
- 21 リフォームでも断熱性能を上げられますか?
- 22 まとめ
長期優良住宅の断熱等級とは?

長期優良住宅では、住宅の耐久性や省エネ性が厳しく求められます。なかでも「断熱等級」は、快適性と光熱費を左右する重要な指標です。住宅の断熱性能を数値化したもので、国が定めた基準に基づき評価されます。
ここではまず、長期優良住宅と断熱等級の関係を整理します。
長期優良住宅とは?
長期優良住宅とは、長く安心して暮らせるよう、国が性能基準を定めて認定する住宅のことです。
1.長期優良住宅とは
(1)制度の概要
長期優良住宅は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置講じられた優良な住宅です。
長期優良住宅の建築及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁に申請することで認定を受けることができます。
新築住宅の認定は平成21年6月4日から、既存住宅を増築・改築する場合の認定は平成28年4月1日から、増築・改築しない場合の認定はR4年10月1日から開始しています。
耐震性・省エネ性・劣化対策・維持管理など、9項目の基準をすべて満たす必要があります。特に断熱性能は、住まいの快適さとエネルギー効率を左右するため、重要視されています。
断熱等級とは?
断熱等級とは、住宅の断熱性能を数値で示す国の基準です。
等級は1から7まであり、数字が高いほど断熱性能が優れています。例えば、等級4は旧省エネ基準、等級5はZEH水準、等級6・7はより高性能な「次世代ZEH基準」にあたります。
断熱等級が高い家は、冬でも室内の温度差が少なく、夏の冷気も逃がしにくいのが特徴です。冷暖房の効率が上がり、年間の光熱費を抑えられるほか、結露やカビの発生を防ぎやすくなります。
つまり断熱等級とは、快適さと省エネ性を客観的に示す「住まいの温度性能スコア」といえるでしょう。
長期優良住宅には断熱等級5以上が必要

長期優良住宅の認定を受けるには、断熱等級5以上を満たすことが条件です。等級5は「ZEH(ゼロエネルギー住宅)」と同水準で、省エネ性が非常に高い住宅性能を意味します。
2025年4月から省エネの観点で法律が改正されたことで、住宅建設の基準が大幅に見直され、これまでの最高等級であった等級4が最低等級になりました。また、断熱等級5から7が新設され、さらに高い断熱性能が求められています。
2030年からは等級5が最低等級になると言われており、断熱性能の高い断熱材を選ぶことが求められます。
長期優良住宅の断熱性能を高めるポイント

断熱等級5を満たすためには、設計段階から断熱・気密・換気を一体的に考えることが欠かせません。
ここでは、長期優良住宅の断熱性能をさらに高めるための実践的な方法を紹介します。
|
▼長期優良住宅の断熱性能を高めるポイント
|
断熱材の種類と厚みを最適化する
断熱性能を高めるためには、気候や建物の形状に合わせて断熱材を選び、適切な厚みで施工することが欠かせません。
寒冷地では外気の影響を受けにくい素材が求められ、温暖地では湿気に強い断熱材が適しています。
断熱材にはグラスウールやウレタンフォーム、セルロースファイバーなどがあり、それぞれ熱伝導率や耐湿性が異なります。どの素材を選ぶかよりも、すき間のない丁寧な施工が重要です。
施工の際に小さな空間ができると、熱が逃げやすくなり、断熱性能が大きく低下します。壁や天井、床下まで断熱層を連続させることで、外気との温度差を最小限に抑えられます。
また、地域や構造によって最適な厚みは異なるため、専門家が建物全体の熱の流れを考慮して設計することが大切です。
換気計画と結露対策で性能を長持ちさせる
断熱性能を長く保つためには、計画的な換気と結露対策を組み合わせることが重要です。
どれほど高性能な断熱材を使用しても、湿気がこもると内部結露が起こり、性能が低下してしまいます。壁や屋根の内部に水分が残ると、カビや腐食が進行し、構造体の寿命を縮める原因にもなります。
対策として、熱交換型の24時間換気システムを採用すると、外気を取り込みながら室温を一定に保てます。さらに、壁体内に通気層を設けることで、湿気を外へ逃がしやすくなり、断熱材を乾燥した状態に保てます。
また、断熱材自体も吸湿しにくい素材を選ぶと、結露リスクを抑えやすくなります。
窓やサッシの断熱性能を強化する
住宅の断熱性能を高めるうえで効果が大きいのが窓まわりの見直しです。
壁や床に比べて熱の出入りが多く、室内の温度環境を左右する大きな要因になります。冬は暖かい空気が逃げ、夏は外からの熱が侵入しやすいため、窓の断熱対策が重要です。
また、窓の配置や方角の工夫も断熱性に大きく影響します。南面には採光を確保しつつ日射を取り込む設計を行い、東西面では遮熱を重視するのが理想です。
軒や外付けブラインドを組み合わせると、季節ごとの日射をうまくコントロールできます。
気密性を高めて断熱効果を最大化する
断熱材の性能を十分に発揮させるには、建物全体の気密性を高めることが欠かせません。いくら高性能な断熱材を使用しても、すき間から空気が漏れれば熱は逃げてしまいます。
気密性は断熱性能と密接に関係し、両者を同時に確保することで初めて快適な室内環境が実現します。
施工段階では、サッシや配管まわりなど空気が通りやすい部分を丁寧に処理します。
防湿シートや気密テープを適切に使い、すき間を徹底的にふさぐことが重要です。
実測・点検で性能を維持・改善する
住宅の断熱性能は、完成時が最も高く、その後は経年とともに変化します。
断熱材の沈下やすき間、結露による劣化が起こると、性能は徐々に低下していきます。そのため、建築後も定期的に実測や点検を行い、現状を確認することが大切です。
また、定期的な点検は、断熱だけでなく建物全体の劣化を早期に見つける効果もあります。小さな不具合を放置せずに改善することが、長期優良住宅の価値を保つ第一歩です。
長期優良住宅の断熱性能を高める際の注意点

断熱性能を高めるほど、住宅は快適で省エネになります。ただし、性能を追求する過程でコストや設計上の課題も生じます。
ここでは、長期優良住宅の断熱性能を向上させる際に知っておきたい3つの注意点を紹介します。
|
▼長期優良住宅の断熱性能を高める際の注意点
|
断熱等級を上げると建築費用は上昇する
断熱等級を上げると、一般的に建築費用は増加します。高性能な断熱材やトリプルガラス、熱交換換気システムなどの採用が必要になるためです。
ただし、初期費用は上がりますが、冷暖房費の削減効果を考慮すれば、長期的には十分に回収できます。
また、断熱材のグレードを上げるだけでなく、施工精度の確保にも費用がかかります。すき間のない丁寧な施工や気密測定など、品質を保つための工程を省くことはできません。
そのため、費用だけで判断せず、建物全体の性能バランスを重視することが重要です。
長期優良住宅の施工実績がある会社を選ぶ
断熱性能の高さは、設計よりも施工の精度に左右されます。どんなに良い断熱材を使っても、隙間や施工ミスがあれば性能は発揮できません。
そのため、長期優良住宅の施工実績がある会社を選ぶことが不可欠です。
施工実績のある工務店やハウスメーカーは、最新の断熱基準や測定方法を理解しています。さらに、気密測定や断熱診断を自社で行える体制を持っている場合は信頼性が高いです。
契約前には、どの等級で設計しているのか、実際のUA値やC値の測定を行っているかを確認しましょう。
高性能化は換気計画と必ずセットにする
断熱性能や気密性能を高めるほど、室内の空気がこもりやすくなります。換気計画が不十分だと、湿気や二酸化炭素が溜まり、快適性が損なわれてしまいます。
そのため、高性能化を目指す際には、換気システムの設計を同時に検討することが不可欠です。
また、湿度を一定に保つことで、断熱材や木材の劣化を防ぐ効果もあります。
断熱と換気の2つをバランスよく設計することで、快適で健康的な住環境を実現できます。
長期優良住宅の断熱性能に関するよくある質問
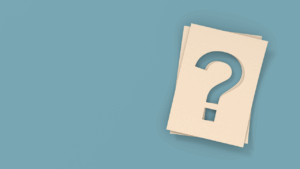
断熱性能は住宅の快適性や光熱費に直結するため、疑問を持つ方が多い分野です。
ここでは、長期優良住宅を検討する際に知っておきたい断熱性能の基準や注意点を、分かりやすくQ&A形式で解説します。
|
▼長期優良住宅の断熱性能に関するよくある質問
|
長期優良住宅に必要な断熱等級はいくつですか?
現在の基準では、断熱等性能等級5以上が必須です。
2030年からは等級5が最低等級になるとも言われており、断熱性能の高い断熱材を選ぶことが求められます。
断熱等級を上げるとどれくらい費用が変わりますか?
断熱等級を上げると、建築費用は一般的に数十万円から数百万円上昇します。高性能な断熱材やトリプルガラス、熱交換換気システムなどを導入するためです。
ただし、冷暖房のエネルギー消費量が減るため、光熱費の削減効果が得られます。年間2〜3万円の省エネ効果が見込めるケースも多く、10年程度で差額を回収できることがあります。
長期優良住宅はZEH住宅とどう違うのですか?
ZEH住宅は、太陽光発電などで家庭内のエネルギー消費を実質ゼロにする住宅です。
一方、長期優良住宅は省エネ性だけでなく、耐震性・劣化対策・維持管理のしやすさなど、総合的な品質を評価します。
つまり、ZEHは「エネルギー効率」に焦点を当てた基準、長期優良住宅は「住宅の長寿命化と環境配慮」を重視した制度です。
断熱性能を高めると夏は暑くなりませんか?
断熱性が高い住宅でも、正しく設計すれば夏の暑さを抑えられます。断熱は「熱を通しにくくする性能」であり、外の熱を遮る効果もあります。
ただし、日射遮蔽が不十分だと、太陽光で室温が上昇する場合があります。そのため、Low-Eガラスや外付けブラインド、庇などを組み合わせ、季節ごとの日射コントロールを行うことが大切です。
断熱材の種類で性能はどのくらい変わりますか?
断熱材の種類によって熱の伝わり方や耐湿性が異なります。一般的に、ウレタンフォームは高い断熱性を持ち、グラスウールはコストパフォーマンスに優れています。
ただし、素材そのものの性能よりも施工精度の影響が大きい点に注意が必要です。小さなすき間や結露があるだけで、断熱性能は大きく低下します。
素材特性を理解し、精度の高い施工を行うことが、長期的に性能を維持するためのポイントです。
リフォームでも断熱性能を上げられますか?
既存住宅でも、断熱リフォームによって性能を向上させることが可能です。壁の内側や天井裏に断熱材を追加したり、床下を改修したりする方法があります。
また、内窓を設置することで熱損失を抑え、気密性を高めることもできます。外壁を壊さずに吹付断熱を行う工法なら、工期を短縮しながら効果的に断熱性を高められます。

フォームライトSLは、現場発泡させる吹き付けウレタンフォームです。壁の中を隙間なく断熱材で充填できるため、快適な居住空間を作り出すことができます。断熱等級の最高水準7に対応している点もポイントです。
フォームライトSLの特徴は以下の通りです。
- 優れたコストパフォーマンス
- ランニングコストが経済的
- 断熱工事と気密工事を同時対応できるため工期はおよそ2日間
断熱材選びに迷われている方は、ぜひ詳細が記載されたカタログをダウンロードしてみてください。
まとめ
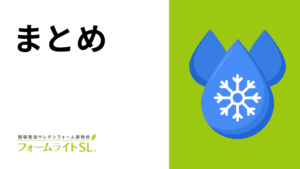
本記事では、長期優良住宅における断熱等級の基準や、性能を高めるためのポイントを解説しました。
断熱等級5以上を満たすことで、省エネ性・快適性・耐久性が向上します。素材選びや施工精度、換気計画を一体的に考えることが、長く快適に暮らせる家づくりの基本です。
性能を維持するためには、定期的な点検やメンテナンスも欠かせません。基準を理解し、信頼できる施工会社とともに、未来を見据えた高性能住宅を実現しましょう。