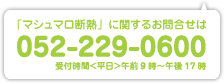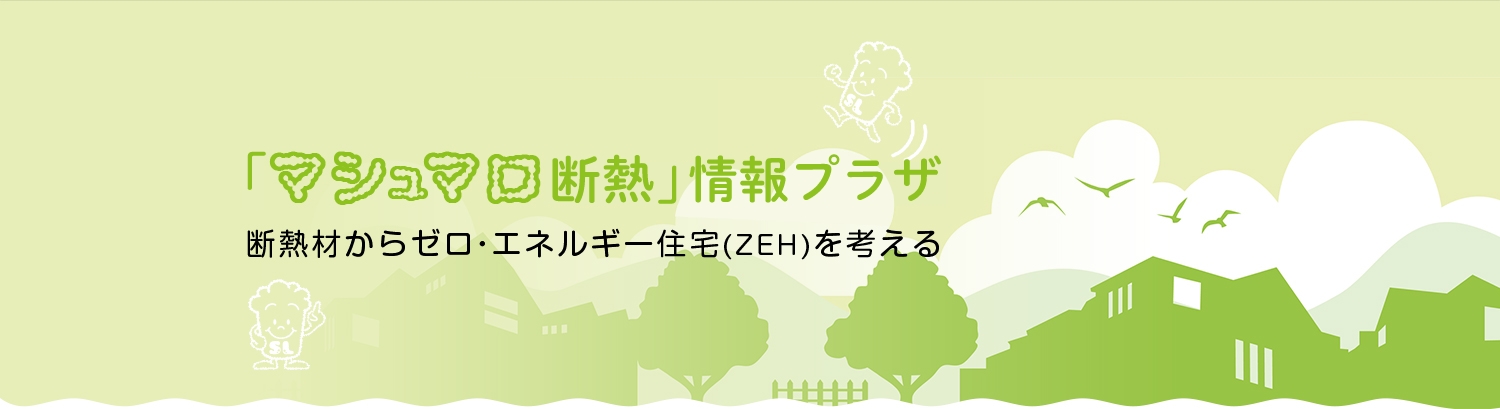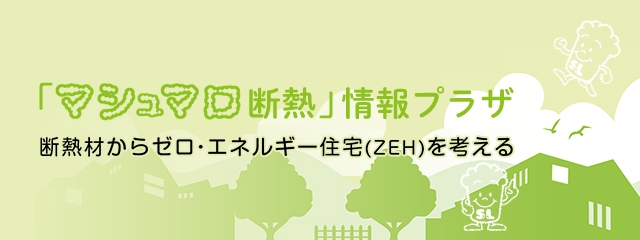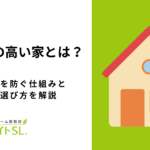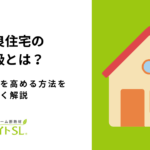断熱材は、家の快適さや省エネ性能を大きく左右する重要な素材です。種類ごとに性能や施工のしやすさ、価格が異なり、選び方を間違えると光熱費や住み心地に影響します。
適切な断熱材を選べば、冬は暖かく夏は涼しい環境を保ち、長期的にエネルギーコストも抑えられます。
本記事では、断熱材をランキング形式で比較し、それぞれの特徴や向いている用途を詳しく解説します。
この記事を読むことで、自宅や建築計画に合った断熱材を自信を持って選べるようになります。

フォームライトSLは、現場発泡させる吹き付けウレタンフォームです。壁の中を隙間なく断熱材で充填できるため、快適な居住空間を作り出すことができます。
フォームライトSLの特徴は以下の通りです。
- 優れたコストパフォーマンス
- ランニングコストが経済的
- 断熱工事と気密工事を同時対応できるため工期はおよそ2日間
断熱材選びに迷われている方は、ぜひ詳細が記載されたカタログをダウンロードしてみてください。
目次
- 1 断熱材ランキングTOP9
- 2 1位|グラスウール
- 3 2位|硬質ウレタンフォーム
- 4 3位|フェノールフォーム
- 5 4位|炭化コルク
- 6 5位|ロックウール
- 7 6位|羊毛
- 8 7位|セルロースファイバー
- 9 8位|押出法ポリスチレンフォーム
- 10 9位|インシュレーションボード
- 11 断熱材を選ぶ際の6つのポイント
- 12 熱伝導率で性能を見極める
- 13 気密性の高さを確認する
- 14 施工方法と現場対応力を考慮する
- 15 耐久性・経年劣化リスクを把握する
- 16 価格とコストパフォーマンスを比較する
- 17 使用部位との適合性を確認する
- 18 断熱材に関するよくある質問
- 19 断熱材は複数種類を使っても大丈夫?
- 20 熱伝導率とは何ですか?
- 21 断熱材の厚みを増やせば性能は上がりますか?
- 22 まとめ
断熱材ランキングTOP9

住宅の断熱性を高めるには、性能や施工性だけでなく、素材の特性や価格帯を把握することが重要です。
以下の表では、主要な断熱材9種類をジャンル別に整理し、特徴や価格帯を比較したものです。
|
順位 |
名称 |
ジャンル |
説明 |
価格帯 |
|
1位 |
グラスウール |
無機繊維系 |
ガラス繊維を綿状に加工した断熱材 |
安め |
|
2位 |
硬質ウレタンフォーム |
発泡プラスチック系 |
ポリウレタン樹脂を発泡させてつくる高断熱材 |
やや高め |
|
3位 |
フェノールフォーム |
発泡プラスチック系 |
フェノール樹脂に発泡剤や硬化剤を加えて成形 |
かなり高め |
|
4位 |
炭化コルク |
天然素材系 |
コルク端材を炭化加工し、調湿性と断熱性を備える |
高め |
|
5位 |
ロックウール |
無機繊維系 |
鉱物を高温で溶かし繊維化。耐火性・吸音性に優れる |
安め |
|
6位 |
羊毛 |
天然素材系 |
羊毛を防虫処理し断熱材化。吸放湿性が高い |
高め |
|
7位 |
セルロースファイバー |
木質繊維系 |
新聞紙や木質原料を再利用した断熱材。吸音・調湿性が高い |
やや高め |
|
8位 |
押出法ポリスチレンフォーム |
発泡プラスチック系 |
ポリスチレン樹脂を発泡成形。耐水性と加工性が高い |
やや高め |
|
9位 |
インシュレーションボード |
木質繊維系 |
木材繊維を圧縮成形。調湿性と断熱性を併せ持つ |
中程度 |
1位|グラスウール
グラスウールは、多くの木造住宅で採用されるガラス繊維を綿状に加工した断熱材です。ガラスを高温で溶かし、髪の毛よりも細い繊維にして綿状に成形します。耐火性や吸音性にも優れ、幅広い住宅構造に対応できる点が強みです。
ただし、繊維内部に湿気が入り込むと断熱性能が大きく低下します。そのため、通常は気密フィルムで包み湿気を遮断しますが、施工時にタッカーや釘で留める際にフィルムを損傷してしまう事例もあります。防湿対策を確実に行うことが、長期的な性能維持には不可欠です。
価格帯は比較的安価で入手しやすく、コストパフォーマンスにも優れます。適切な施工を行えば、長期にわたり安定した断熱効果を発揮できる素材です。
2位|硬質ウレタンフォーム
硬質ウレタンフォームは、ポリウレタン樹脂を発泡させて作られる断熱材です。発泡構造により空気を多く含み、高い断熱性を発揮します。軽量で加工がしやすく、耐水性や耐久性にも優れています。
主に現場吹付けタイプとボード状タイプがあります。吹付けタイプは現場で発泡させながら施工するため、建物の形状に合わせて隙間なく充填でき、高い気密性を確保できます。ボード状タイプは工場で成形されるため品質が安定しており、必要に応じて現場でカットして使用します。
価格はやや高めですが、省エネ性を重視した住宅や高性能住宅に適しています。
3位|フェノールフォーム
フェノールフォームは、フェノール樹脂に発泡剤や硬化剤を加えて成形した断熱材です。熱を受けると硬化し、形状を保ちやすい特性があります。
高い断熱性能を持ち、建物外側で熱を遮断する外張り断熱工法に多く採用されます。吸水性が低く、湿気による性能劣化も少ないため、長期間安定した効果を発揮できる点も魅力です。
ただし、価格は他の断熱材と比べてかなり高く、1㎡あたりのコストも上昇します。採用する際は、予算とのバランスを十分に検討することが欠かせません。
4位|炭化コルク
炭化コルクは、ワインボトルなどに使われるコルクの端材を高温で炭化させて成形した断熱材です。天然素材由来のため、化学物質の使用が少なく、環境負荷の低さが特徴です。
断熱性能に加え、高い調湿性を備えており、室内の湿度を安定させる効果があります。
一方で、価格は高めで、他の天然素材系断熱材と同等かそれ以上のコストがかかります。そのため、採用する場合は予算計画をしっかり立てる必要があります。
5位|ロックウール
ロックウールは、玄武岩や高炉スラグなどの岩石を高温で溶かし、繊維状に加工した断熱材です。構造や性能はグラスウールに近く、耐火性や吸音性に優れています。
燃えにくく、熱にも強いため、火災時の延焼リスクを低減できる点が特徴です。
価格は比較的安価ですが、同じ無機繊維系であるグラスウールよりやや高めです。耐火性や耐湿性を重視する住宅や施設に適しており、長期的な安全性と快適性を両立できる断熱材です。
6位|羊毛
羊毛断熱材は、原料となる羊毛に防虫処理を施して製造されます。湿度が高いときは水分を吸収し、乾燥時には放出する調湿性を備えており、室内環境の快適さを保ちやすい素材です。
天然素材ならではの柔らかさと安全性があり、化学物質を避けたい住宅やエコ志向の建築に適しています。
一方で、価格は他の断熱材と比べてかなり高めです。導入時にはコスト負担が大きくなりますが、環境負荷の低さや快適性の高さを重視する場合には有力な選択肢となります。
7位|セルロースファイバー
セルロースファイバーは、新聞紙や段ボール、おがくずなどの木質原料を再利用して作られる断熱材です。自然素材を主成分としているため、製造や廃棄時の環境負荷が低い点が特徴です。断熱性能に加えて調湿性や吸音性にも優れ、室内環境を快適に保つ効果があります。
木質素材であるため虫食いや腐食の懸念がありますが、製造段階でホウ酸や硫酸アンモニウムを添加し、防虫性と難燃性を向上させています。
ただし、セルロースファイバーは形がないため、吹き込み施工をした際に隙間から材料が落ちてしまい気密性が低くなるといったデメリットもあります。
他の断熱材と比較して、価格帯はやや高めです。
8位|押出法ポリスチレンフォーム
押出法ポリスチレンフォームは、ポリスチレン樹脂を発泡させて作られる断熱材です。軽量で加工がしやすく、施工現場での取り扱いが容易なため、住宅の壁や屋根、床など幅広い部位に採用されています。
吸水性が低く、湿気や水分の影響を受けにくいことから、床下や基礎周りなど湿気の多い環境にも適しています。
一方で熱には弱く、高温環境では変形や性能低下が生じる可能性があるため、防火性能を確保する仕上げ材や構造設計が求められます。
価格はやや高めですが、耐水性と加工性のバランスに優れた断熱材です。
9位|インシュレーションボード
インシュレーションボードは、木材を細かく砕いた繊維を圧縮・成形して作られる断熱材です。環境負荷が比較的低く、自然素材を活用した建築やエコ住宅に適しています。
一方で、湿度の高い環境ではカビや寸法変化が生じる可能性があります。使用する場合は、防湿施工や換気計画をしっかり行うことが重要です。製品によっては透湿性や防カビ性能を備えたタイプもあるため、設置環境に合わせた選定が求められます。
断熱材を選ぶ際の6つのポイント

断熱材は種類ごとに性能や特徴が異なり、建築部位や予算に合った選択が重要です。
ここでは、長期的に快適な住環境を保つために押さえておきたい6つの選定基準を解説します。
|
▼断熱材を選ぶ際の6つのポイント
|
熱伝導率で性能を見極める
断熱材の性能を評価する際、基本となる指標が熱伝導率です。数値が小さいほど熱を通しにくく、高い断熱効果を発揮します。熱伝導率は素材や密度、含水率によって変化するため、カタログ値だけでなく施工環境も考慮する必要があります。
また、厚みを増すことで断熱性は向上しますが、施工可能なスペースとのバランスを取ることが大切です。
熱伝導率の低い断熱材は初期コストが高くなりがちですが、省エネ性や快適性を長期的に確保できます。建築用途や地域の気候条件を踏まえ、必要な断熱性能を満たす素材を選びましょう。
気密性の高さを確認する
断熱効果を最大限に発揮するには、断熱材そのものの性能だけでなく、施工後の気密性も欠かせません。気密性が低いと、隙間から暖気や冷気が逃げ、光熱費の増加や結露の発生につながります。
吹付けタイプの断熱材は構造に密着しやすく、複雑な形状の部分でも隙間を減らせます。一方、ボード状やマット状の場合は、継ぎ目や端部の処理を丁寧に行うことが必要です。
また、気密シートや防湿フィルムを組み合わせることで、湿気の侵入を防ぎつつ気密性を向上できます。
施工品質は職人の技術に左右されやすいため、経験豊富な施工業者を選ぶことが重要です。断熱材の種類選びと同時に、現場での施工精度を確保する体制を確認しましょう。
施工方法と現場対応力を考慮する
断熱材の選定では、素材の性能だけでなく施工方法や現場での対応力も重要です。
吹付けタイプは形状に合わせて隙間なく施工できる反面、専門の施工機材や技術者が必要になります。ボード状やマット状は扱いやすく、現場での加工が可能ですが、隙間や継ぎ目処理を丁寧に行わなければ気密性が低下します。
また、施工環境によっても選択肢は変わります。狭小部や配管周りなど複雑な部位は柔軟性の高い素材が適し、大面積を一度に施工する場合は大判のパネルが効率的です。
工期や施工精度は建物全体の性能に直結するため、採用する断熱材の工法が現場条件や施工業者のスキルに適合しているかを事前に確認することが重要です。
耐久性・経年劣化リスクを把握する
断熱材は長期間にわたり安定した性能を維持することが求められます。素材によっては湿気や圧縮、紫外線などで性能が低下する場合があり、経年劣化の程度は断熱材の種類ごとに異なります。
例えば、繊維系断熱材は湿気を含むと性能が低下しやすく、防湿対策が不可欠です。
また、動物や虫による食害リスクがある天然素材系は、防虫処理や定期的な点検が必要です。耐用年数や保証内容を確認し、使用部位や環境に応じた素材を選ぶことが、長期的なコスト削減と快適性維持につながります。
価格とコストパフォーマンスを比較する
断熱材の価格は素材や性能、施工方法によって大きく異なります。初期費用だけで判断すると、性能不足や早期劣化で結果的にコストが高くなる場合があります。
そのため、ライフサイクルコストでの比較が重要です。ライフサイクルコストとは、買ってから手放すまでにかかる全部の出費を足した金額です。
高性能な断熱材は導入費用が高くても、省エネ効果による光熱費削減や快適性向上で長期的にメリットを得られます。
価格と性能、耐用年数、施工性を総合的に比較し、最適なコストパフォーマンスを実現できる断熱材を選ぶことが重要です。
使用部位との適合性を確認する
断熱材は使用部位によって求められる性能や条件が異なります。屋根や外壁など外気に接する部位では、断熱性能だけでなく耐湿性や耐久性が重要です。床下や基礎部分では耐水性や圧縮強度が求められ、天井や内壁では吸音性や施工性が重視されます。
また、断熱方法が内断熱か外断熱かによっても適した素材が変わります。外断熱では耐候性や防火性が必要で、内断熱では室内側の結露対策が不可欠です。
使用環境や部位に合わない断熱材を選ぶと、性能低下やトラブルの原因となります。設計段階で各部位の条件を整理し、それに適合する断熱材を選定することで、建物全体の性能を最大限に引き出せます。
断熱材に関するよくある質問

断熱材は種類や施工方法が多岐にわたり、選び方や使い方に迷う人も少なくありません。ここでは、特に相談の多い3つの疑問について、専門的な視点からわかりやすく解説します。
|
▼断熱材に関するよくある質問
|
断熱材は複数種類を使っても大丈夫?
基本的に、異なる種類の断熱材を組み合わせて使うことは可能です。外断熱と内断熱を併用する「ダブル断熱」もその一例です。
ただし、素材によって熱の伝わり方や湿気の移動特性が異なるため、組み合わせ方を誤ると結露やカビの原因になります。
そのため、設計段階で断熱材の配置や防湿層の位置を明確に決めることが重要です。複数の断熱材を使う場合は、熱抵抗値や透湿性のバランスを考慮し、施工業者や建築士と相談しながら選定することをおすすめします。
熱伝導率とは何ですか?
熱伝導率とは、熱の伝わりやすさを示す数値で、単位は「W/m・K」で表されます。この値が小さいほど熱を通しにくく、断熱性能が高いことを意味します。
断熱材を選ぶ際には重要な性能指標の一つですが、数値だけで判断するのは避けるべきです。実際の断熱効果は、厚みや密度、防湿性能、施工品質にも左右されます。また、断熱材が湿気を含むと熱伝導率が上がり(性能が下がり)やすい素材もあります。
そのため、熱伝導率は目安としつつ、住宅の構造や使用環境に合った素材選びを行うことが重要です。
断熱材の厚みを増やせば性能は上がりますか?
断熱材は厚みを増やせば断熱性能も高まりますが、必ずしも比例して効果が向上するわけではありません。ある程度の厚みを超えると、追加した分の効果が少なくなる「限界効用」の状態になります。
また、厚みを増やすことで施工スペースが狭くなり、構造やデザインに制約が生じる場合もあります。さらに、厚みよりも隙間なく施工することや、気密・防湿対策を徹底することの方が効果的なケースもあります。
断熱材の最適な厚みは、地域の気候条件や建物の断熱仕様、省エネ基準などを考慮して決定する必要があります。建築士や施工業者と相談し、過不足のない厚みを選びましょう。
フォームライトSLは、現場発泡させる吹き付けウレタンフォームです。壁の中を隙間なく断熱材で充填できるため、快適な居住空間を作り出すことができます。
フォームライトSLの特徴は以下の通りです。
- 優れたコストパフォーマンス
- ランニングコストが経済的
- 断熱工事と気密工事を同時対応できるため工期はおよそ2日間
断熱材選びに迷われている方は、ぜひ詳細が記載されたカタログをダウンロードしてみてください。
まとめ
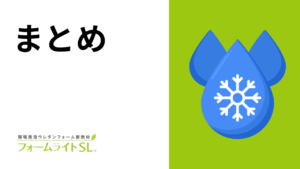
本記事では、断熱材ランキングTOP9を性能・施工性・価格の観点から比較し、それぞれの特徴や適した用途を解説しました。
断熱材は、建物の快適性や省エネ性能を左右する重要な要素です。素材ごとに断熱性能や耐久性、施工性、価格が異なるため、ライフサイクルコストも含めた総合的な判断が欠かせません。また、建築部位や気候条件、防湿・気密対策の有無によっても最適な選択肢は変わります。
最終的には、住宅の設計方針や予算、長期的な運用コストを踏まえ、信頼できる施工業者や建築士と相談しながら選定することが重要です。適切な断熱材を選び、適切に施工することで、四季を通じて快適でエネルギー効率の高い住まいを実現できます。